こんにちは、ヨーダです。
突然ですが、あなたは毎日「やること」に追われていませんか? ToDoリストが膨らむほど、心も体も疲れ切ってしまうものです。そんなときにこそ役立つのが「やらないことリスト」。やることを増やすのではなく、やめることを決めるだけで、驚くほど心と時間に余裕が生まれます。
この記事では効果や実践法、具体例をわかりやすく紹介します。
やらないことリストで変わる3つの効果
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 時間と心に余裕が生まれる
- 本当に大切なことに集中できる
- 人間関係や習慣がシンプルになる

「やらないことリスト」は単なる効率化の方法ではなく、人生全体を整える考え方です。余計な負担を減らすことで心と時間の余裕が生まれ、集中力も高まり、人間関係や習慣もスッキリします。ここでは代表的な3つの効果を解説します。
時間と心に余裕が生まれる
最大の効果は「ゆとり」が戻ってくることです。私たちは気づかないうちに重要でない作業や習慣に多くの時間を使っています。例えば、惰性で続けている会議参加や、義務感だけの習慣などです。
これらをやめれば、その時間を本当に必要なことに使えます。また「やらなければ」と思うことが減るため、焦りや罪悪感に追われず、自然と気持ちが落ち着きます。その結果、毎日の行動にメリハリが生まれ、生活の満足度が上がります。
本当に大切なことに集中できる
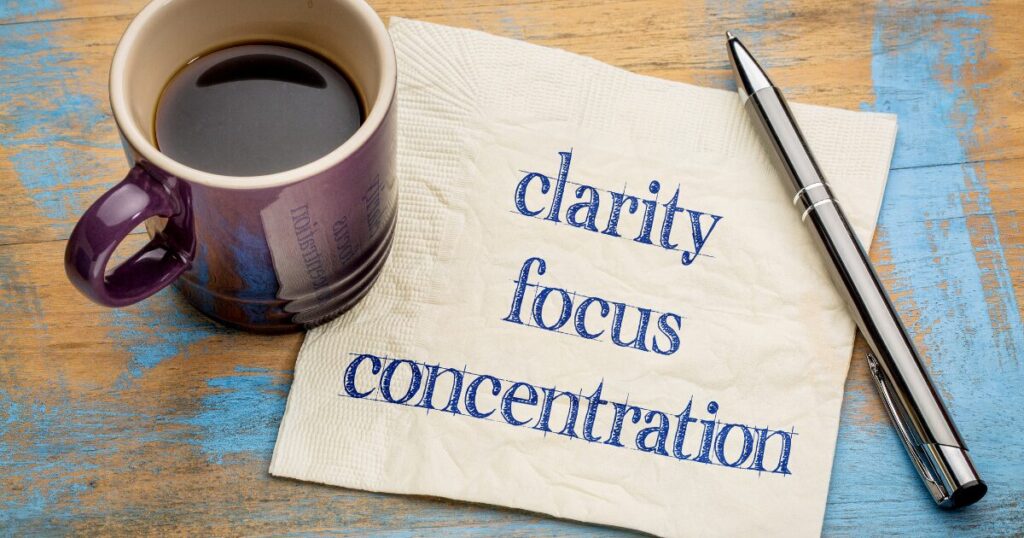
「やらない」と決めると、限られた時間やエネルギーを優先すべきことに集中できます。多くの人は重要度の低い雑務や他人に合わせる行動に流されがちですが、あらかじめ線引きしておくことで本質的な活動に力を注げます。
例えば、ムダな会議やSNSチェックをやめると、その分をスキルアップや家族との時間に使えます。やるべき対象が明確になると達成感が増し、自信も高まります。結果として日々の充実度がぐっと高まるのです。
人間関係や習慣がシンプルになる
「やらないことリスト」には、人間関係や生活習慣の見直し効果もあります。私たちは「断れない」「続けないといけない」と思い込み、無意識に負担を抱えていることが少なくありません。
例えば、必要以上に気を使う飲み会や、何となく続けている生活習慣を見直せば、自分にとって大切な人や役立つ習慣に時間を割けるようになります。関係や習慣がシンプルになると、心の疲れも減り、気持ちを前向きに保ちやすくなるのです。
“やめる勇気”を後押しする👉 『人生をシンプルにする“やめる”習慣』を楽天ブックスで見る
 | エッセンシャル思考 最少の時間で成果を最大にする [ グレッグ・マキューン ] 価格:1760円 |
やらないことリストを実践する4つのステップ
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 現状の行動・習慣をすべて洗い出す
- 必要・不要を「価値観」で仕分ける
- 「やらない」と決める勇気を持つ
- 定期的に見直して軌道修正する

やらないことリストは思いつきで作るより、手順を踏んで整理する方が効果的です。まずは行動を見える化し、価値観を基準に必要かどうかを判断。そのうえで「やめる」と決断し、定期的に見直すことで自分に合った形に育てられます。
現状の行動・習慣をすべて洗い出す
最初のステップは、日常でどんな行動や習慣に時間を使っているかを洗い出すことです。意識せず繰り返している行動も含めて、すべて書き出します。
例としては、
- 一日のスケジュールを時系列で書く
- スマホの使用時間をアプリで確認する
- 家計簿やレシートから無駄な支出を振り返る
ここで重要なのは「良い・悪い」を判断せず、とにかくリスト化すること。現状を把握することが、次の仕分け作業の土台になります。
必要・不要を「価値観」で仕分ける
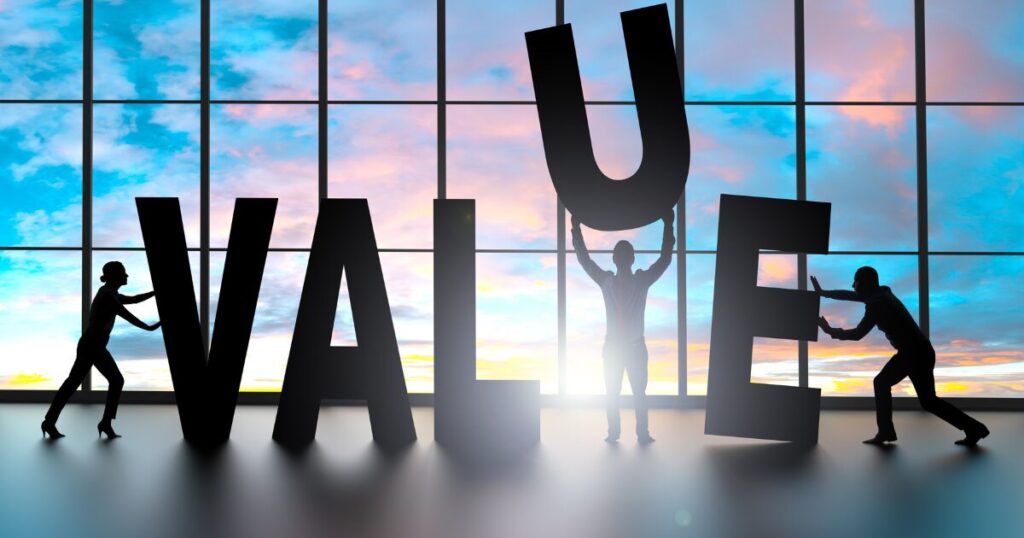
行動を洗い出したら、それを「必要」か「不要」に分けます。このときの基準は社会の常識や他人の意見ではなく、自分自身の価値観です。
例えば、
- 「家族との時間を増やしたい」なら、長時間残業は不要
- 「健康を大事にしたい」なら、夜更かしは不要
自分の軸で仕分けることで、人生にとって本当に必要なものとそうでないものの境界がはっきりします。
「やらない」と決める勇気を持つ
やらないことリストを形だけで終わらせないためには、「やめる」と決める勇気が必要です。「断ったら嫌われるかも」「評価が下がるかも」と不安になる人も多いですが、そのまま続ければ自分の時間やエネルギーが奪われます。
思い切って「やらない」と決めることで、新しい選択肢が生まれます。たとえば惰性の飲み会を断った結果、自分の趣味や学びに時間を使えるようになった人もいます。「やらない」と決めることは逃げではなく、人生を主体的に選ぶための戦略なのです。
定期的に見直して軌道修正する
やらないことリストは一度作って終わりではなく、定期的に見直す必要があります。環境や価値観は変わるため、以前は不要だったものが必要になることもあります。

例えば、子育て中は「夜の飲み会」をやめていた人も、子どもが独立した後には人脈づくりの場として参加する価値が出てくるかもしれません。逆に年齢を重ねれば「夜更かし」や「過度な残業」をやめる優先度が高まります。
こうして定期的に調整することで、常に今の自分に合った選択を維持でき、無理なく続けられる仕組みができます。
無理なく続ける習慣を身につけたい方におすすめ 👉 『Atomic Habits』(ジェームズ・クリア著)を楽天ブックスで見る
 | ジェームズ・クリアー式複利で伸びる1つの習慣 (フェニックスシリーズ) [ ジェームズ・クリアー ] 価格:1650円 |
やらないことリストの具体例5選
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 仕事でやめたいこと(ムダな会議・残業など)
- 副業やフリーランスでやめたいこと(低単価案件など)
- 人間関係でやめたいこと(依存的なつき合いなど)
- 生活習慣でやめたいこと(スマホの使いすぎなど)
- 定年後にやめたいこと(義務感だけの行動など)

やらないことリストは、抽象論より「何をやめるか」を具体化するほど機能します。以下を雛形に、自分の価値観と現実の制約に合わせて微調整してください。
仕事でやめたいこと(ムダな会議・残業など)
目的が曖昧な会議や“とりあえず参加”は、時間も集中力も削ります。会議は成果物(決定事項・次アクション)が出る場に限りましょう。残業も「例外」にとどめると、日中の生産性が上がります。研究でも、会議過多は業務完了を妨げる要因とされ、長時間労働は心血管リスクを高めます。(参考資料:国立がん研究センター)
やらないことリストに書く例
- 目的・アジェンダ・決定者がない会議には参加しない(参加条件を満たさなければ「資料共有で代替」)
- 30分で結論が出ない会議は延長しない(持ち越し時は「誰が・いつまでに」を明記)
- 原則、定時後の残業はしない(例外は“緊急・重要”を満たす案件のみ)
副業やフリーランスでやめたいこと(低単価案件など)
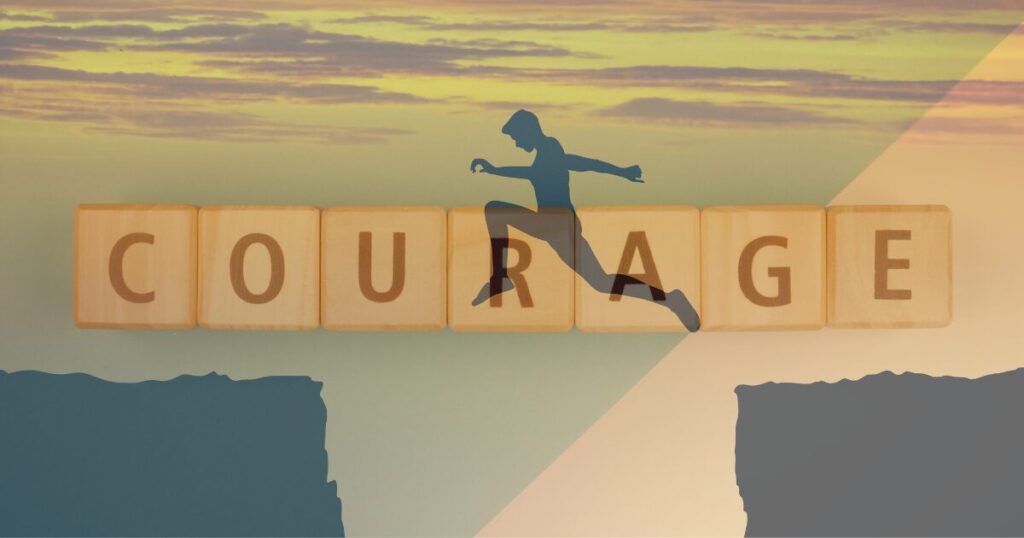
低単価を受け続けると、学習や営業に回す時間が消え、長期的な単価上昇を阻みます。価格は“自分の価値のシグナル”。「案件を選ぶ基準」を先に決め、外れたら受けない勇気を。
やらないことリストに書く例
- 時給換算が○○円未満の案件は受けない(最低ラインを明文化)
- 無償トライアルや過度な仕様追加の無償対応はしない(仕様変更は見積りで対応)
- 主要クライアント依存率を50%超にしない(収益リスク分散のための上限設定)
人間関係でやめたいこと(依存的なつき合いなど)
「断れない」「愚痴の受け皿になり続ける」関係は、エネルギーを奪います。人とのつながりは健康と寿命に関わるほど重要ですが、“量”より“質”が鍵。負担だけ増える関係は線引きしましょう。(参考資料:ライフトピ)
やらないことリストに書く例
- 連絡の既読即返信をやめる(返信は1日○回のバッチ処理に)
- 愚痴だけの通話・会食は受けない(テーマと時間を決めた場だけ参加)
- 「合わない」と感じる関係に罪悪感で関わり続けない(距離の最適化)
生活習慣でやめたいこと(スマホの使いすぎなど)
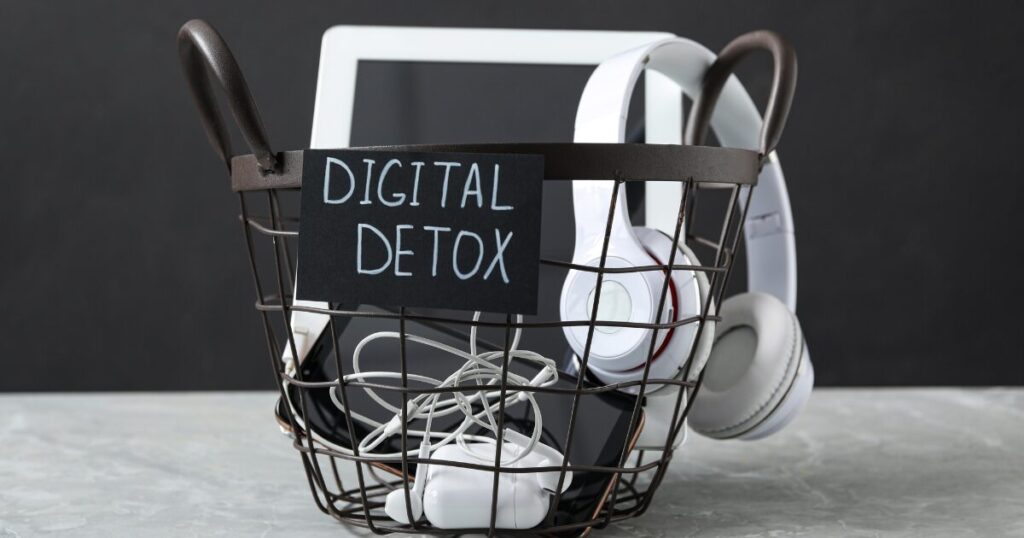
寝る前のダラ見は睡眠の質を下げやすく、翌日の集中力に響きます。電子メディア利用と睡眠の質低下の関連は、多くのレビューで報告されています(原因はブルーライトだけでなく“刺激的な内容”や就寝遅延も)。(参考資料:JHO)
やらないことリストに書く例
- 就寝90分前からスマホを触らない(充電は寝室外/アラームは置時計)
- 食事中のながら視聴をしない(食事は“味わう時間”に)
- 「ながらニュース」をやめ、朝夕に15分だけ“まとめて見る”運用にする
定年後にやめたいこと(義務感だけの行動など)
自由時間が増えると「何かしなきゃ」に陥りがちです。健康や人間関係の質は“選び方”で決まります。長時間労働を離れた後は、体調と気分を基準に活動を選ぶのが合理的。心身への負荷が高い習慣は思い切って手放しましょう(過剰な負担は健康リスク)。(参考資料:労働政策研究・研修機構)
やらないことリストに書く例
- 義務感だけの地域行事・会合には参加しない(参加目的が自分に合うかを毎回確認)
- “なんとなく”のテレビ長時間視聴をしない(1日合計○○分まで)
- 予定のない外出を“罪悪感”で埋めない(“何もしない日”を予定に入れる)
ToDoリストに追われない生き方 👉 『LIFE SHIFT』(リンダ・グラットン著)を楽天ブックスで探す
 | LIFE SHIFT(ライフ・シフト) 100年時代の人生戦略 [ リンダ・グラットン ] 価格:1980円 |
やらないことリストを続けるための3つのコツ
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 小さな「やめる」を積み重ねる
- 家族や仲間に宣言して習慣化する
- ツールやアプリを活用して管理する

やらないことリストは作っただけでは効果が出ません。大切なのは、無理なく続ける仕組みをつくることです。ここでは習慣化を助ける3つのコツを紹介します
小さな「やめる」を積み重ねる
最初から大きなことをやめようとすると挫折しやすくなります。例えば「残業を一切しない」と決めても現実的には難しいでしょう。
代わりに、次のような“小さなルール”から始めると続けやすくなります。
- 「30分以上の残業はしない」
- 「夜10時以降はスマホを見ない」
小さな成功体験を積み重ねることで自信が生まれ、自然と大きな習慣の改善につながります。
家族や仲間に宣言して習慣化する
自分一人で抱え込むよりも、周囲に宣言すると継続しやすくなります。例えば「休日は仕事のメールをしない」と家族に伝えておけば、無意識のうちに守れる環境が整います。
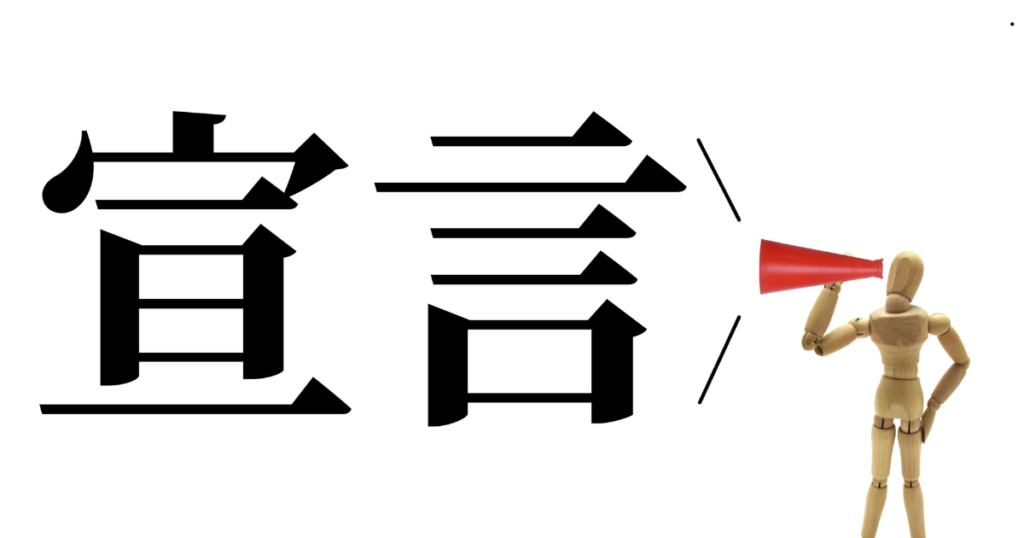
また、SNSなどで「今週は残業ゼロを目指します」と発信するのも有効です。仲間と励まし合える場があると、途中で挫折しにくくなります。宣言はプレッシャーにもなりますが、良い意味で行動を後押ししてくれるのです。
ツールやアプリを活用して管理する
継続にはツールを活用するのも効果的です。紙のノートに書き出す方法も良いですが、スマホアプリやタスク管理ツールを使うと忘れにくくなります。
例えば、
- Googleカレンダーに「夜10時以降はスマホ禁止」と入力してリマインド通知を設定する
- 習慣管理アプリで「やらなかった日」を記録して、ゲーム感覚で進める
このようにツールを味方につけると、やめる習慣を無理なく定着させられます。
自分の時間を取り戻しやりたいことに集中する 👉 『とっぱらう』(ジェイク・ナップ著)を楽天ブックスで見る
 | とっぱらう 自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」 [ ジェイク・ナップ ] 価格:1650円 |
やらないことリストを作るときの注意点
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- やらなさすぎて逆にストレスになるケース
- 他人に押しつけると関係悪化につながる
- 「やめる勇気」が持てないと形骸化する

やらないことリストは便利なツールですが、使い方を誤ると逆効果になることがあります。ここではよくある失敗とその対策を解説します。
やらなさすぎて逆にストレスになるケース
やらないことを増やしすぎると、かえって生活が窮屈に感じることがあります。例えば「テレビを一切見ない」「外食を完全にやめる」と極端に制限すると、息抜きや楽しみがなくなりストレスが溜まります。
大切なのは“ゼロにする”ではなく“減らす”ことです。
- 例:「平日は30分だけテレビを見る」「週末だけ外食を楽しむ」
柔軟なルールにすることで、バランスを崩さず続けられます。
他人に押しつけると関係悪化につながる

やらないことリストはあくまで自分のためのツールです。それを他人に押しつけると、人間関係が悪化する恐れがあります。例えば「私は飲み会に行かないから、あなたもやめるべき」と言うと、相手に干渉しているように受け取られます。
ポイントは「私はやらない」と自分のルールとして示すこと。強制しなくても、自分の行動が周囲に良い影響を与える場合もあります。
「やめる勇気」が持てないと形骸化する
やらないことリストを作っても、「本当にやめられるかな」と不安になり、結局続けてしまうことがあります。例えば「残業を減らす」と書いても、同僚の目を気にして流されれば意味がありません。
効果を出すには、小さくても「断る」「やめる」という行動を実際に起こす勇気が必要です。最初は気まずくても、一度やめてみると「意外と大丈夫だった」と気づくことが多いです。
小さな成功体験を積むことで自信がつき、大きな決断もできるようになります。
断捨離の思考を人生に応用 👉 『ぼくたちに、もうモノは必要ない。』(佐々木典士著)を楽天ブックスでチェック
 | ぼくたちに、もうモノは必要ない。増補版 (ちくま文庫 さー48-1) [ 佐々木 典士 ] 価格:858円 |
人生のステージ別・やらないことリスト活用法
この章で扱う主なポイントは以下のとおりです。
- 30代:キャリアと家庭の両立でやめたいこと
- 40代:中堅期に抱えがちなムダを削る
- 50代:健康と人間関係を見直す
- 60代:定年後の自由な時間を守る「やめる習慣」
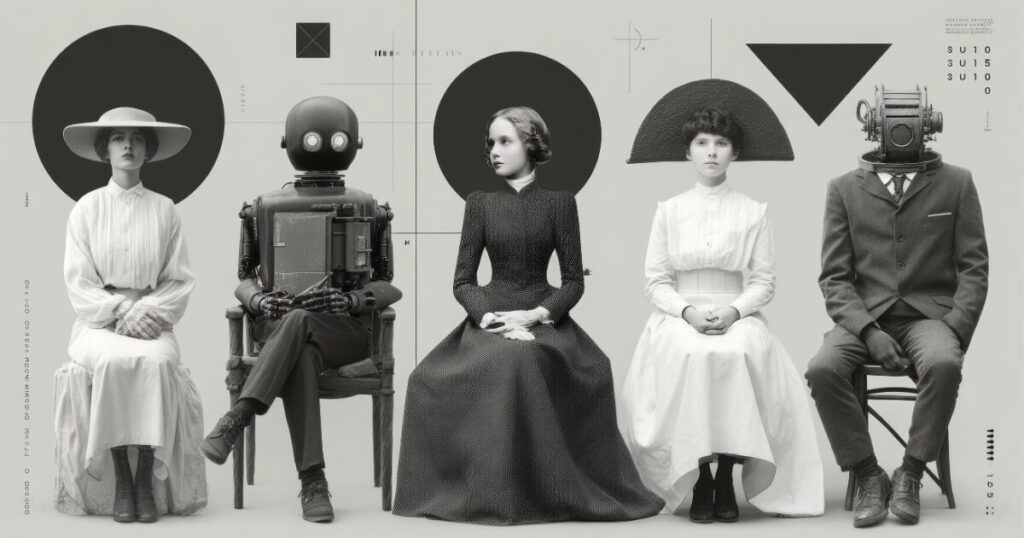
やらないことリストは年齢や環境によって内容が変わります。30代はキャリアと家庭の両立、40代は増える責任、50代は健康や人間関係、60代は自由時間の活かし方がテーマになります。ここでは年代ごとの「やめるべきこと」を整理します。
30代:キャリアと家庭の両立でやめたいこと
30代はキャリアの成長期と同時に、結婚・子育てなど家庭面でも大きな変化が訪れる時期です。この年代でやめたいのは「長時間残業」と「完璧主義」。
- 長時間残業は家庭の時間を削り、疲労も蓄積させます。
- 完璧主義はタスクを増やし、自己否定につながります。
やらないことリスト例
- 定時以降は原則働かない
- すべてを完璧にやろうとしない
小さな割り切りが、仕事と家庭のバランスを整えます。
40代:中堅期に抱えがちなムダを削る

40代は中堅的な立場で責任が増え、タスクや人間関係も膨らみます。この年代でやめたいのは「惰性の会議」と「付き合いだけの飲み会」。
- 目的のない会議は時間の浪費になりがちです。
- 義務感だけの飲み会は疲労を増やします。
やらないことリスト例
- アジェンダのない会議には参加しない
- 義務感だけの飲み会は断る
取捨選択を徹底することが、心身の余裕を守るカギになります。
50代:健康と人間関係を見直す
50代は体調の変化を実感しやすく、人間関係も整理が必要になる時期です。この年代でやめたいのは「不規則な生活」と「気を使いすぎる関係」。
- 夜更かしや偏った食生活は健康リスクを高めます。
- 無理に合わせ続ける関係は精神的な疲労を招きます。
やらないことリスト例
- 夜更かしをしない
- 疲れるだけの付き合いは避ける
健康と人間関係をシンプルに整えることが、定年後の充実につながります。
60代:定年後の自由な時間を守る「やめる習慣」

60代は定年を迎え、自由時間が増える一方で「何かしなければ」という焦りにとらわれがちです。この年代でやめたいのは「義務感だけの活動」と「無計画な時間の浪費」。
- 意味を感じない活動はストレスの原因になります。
- テレビやネットに時間を費やしすぎると自由が逆に窮屈に。
やらないことリスト例
- やりたくない活動には参加しない
- 目的のないだらだら時間は減らす
やらないことを明確にすることで、自由時間を“心から楽しめる時間”に変えられます。
シンプルに生きるヒント 👉 『人生をシンプルにする本』(山田マキ著)を楽天ブックスで見る
 | あーーーーー!!!仕事も人間関係もいろいろめんどくさ!!!と思ったら読む 人生をシンプルにする本 [ 山田 マキ ] 価格:1430円 |
まとめ|「やらないこと」があなたの人生を自由にする
やらないことリストは、限られた時間とエネルギーを守るための強力なツールです。タスクを増やすのではなく、不要なものを削ることで本当に大切なものが見えてきます。
本記事のポイント(5つ)
- やらないことリストは、時間と心の余裕を生み出す。
- 本当に大切なことへ集中できる環境を整えられる。
- 人間関係や習慣をシンプルに保ち、ストレスを減らせる。
- 年代ごとの活用法で、自分に合った効果を発揮できる。
- 続けるには「小さなやめる」「周囲への宣言」「ツール活用」がカギになる。

人生は「やること」を増やすよりも、「やらないこと」を決めることで自由度が広がります。今日から小さな一つでも「やめる」と決めることで、未来の時間と心の使い方が大きく変わり始めるでしょう。
📎 付録:やらないことリスト チェックリスト
✅ すぐ使えるテンプレ(3行版)
印刷して冷蔵庫やデスク横に貼ってもOK!
- 仕事でやらないこと
□ 目的のない会議には参加しない
□ 30分以上の残業はしない - 生活習慣でやらないこと
□ 夜10時以降はスマホを見ない
□ 寝る前の動画視聴をやめる - 人間関係でやらないこと
□ 愚痴だけの付き合いはしない
□ 即返信を強要されない
📅 1週間トライアルプラン
「とりあえず1週間だけ」試すことで、自分に合ったやらないことを見極めましょう。
- Day 1–2:行動を記録
□ 1日の行動・スマホ使用時間・人付き合いをメモする - Day 3–4:不要トップ3を選ぶ
□ 不要だと感じた行動を3つ選び「やらないことリスト」に書く - Day 5:小さく実行
□ 1つだけ「やめる」と決めて試す(例:夜10時以降スマホ禁止) - Day 6:周囲に宣言
□ 家族・仲間・SNSに「やらないこと」を伝える - Day 7:振り返り
□ うまくいったこと/不便だったことをメモし、翌週に調整
関連記事
・人生を後悔しないために──「生きてる間にやってみたいこと」を見つける方法と実践リスト
・孤独こそ最高の資源──“ひとり時間”を味方にする5つの習慣
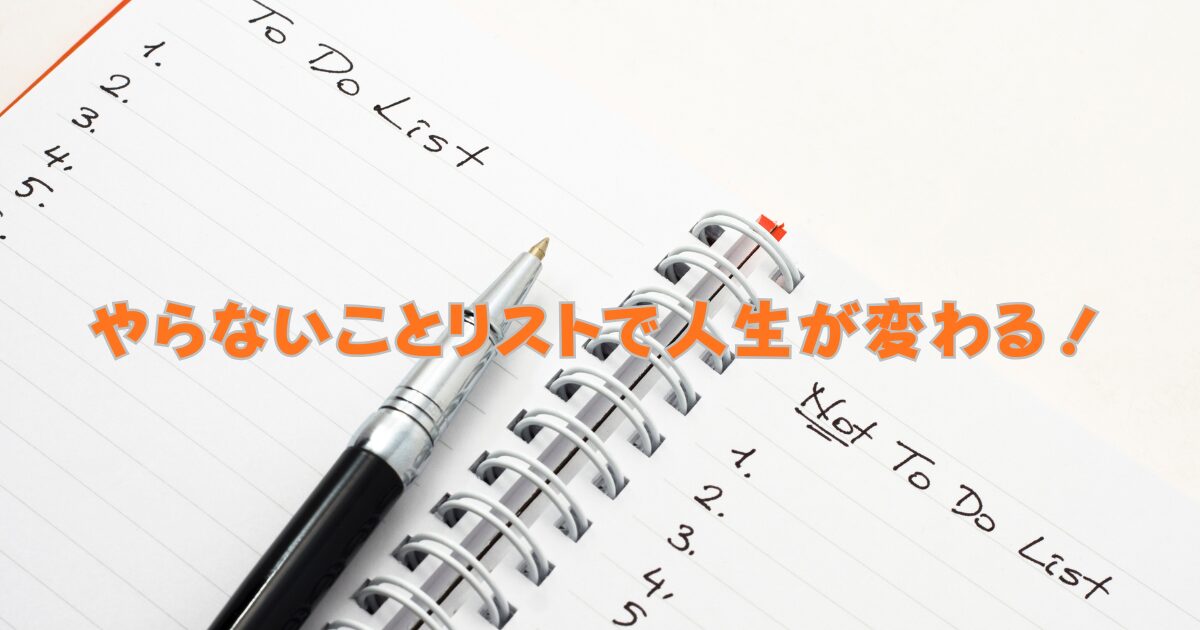


コメント